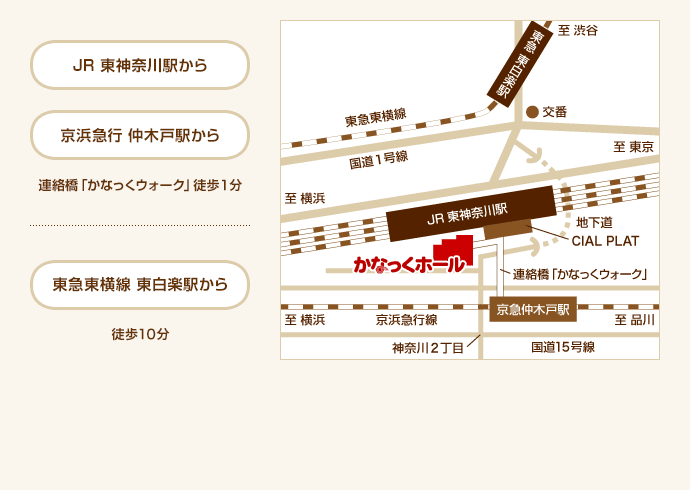昨日は雪の予報でしたが、前回のように大雪が積もらず良かったです。
でもまだ周りにはたくさん雪が残っていて、カチカチに凍っているので日陰は注意が必要な状態が続いています。
この寒い時期ですが、オトシブミの話題です。
昨日は、長池公園生き物図鑑の勉強会で、Kさんが資料を用意してオトシブミの話をしてくれました。
大変興味深い話もあったのでいくつか紹介します。
長池公園生き物図鑑は、誰でも長池で撮影した生き物を投稿することができますが、現在5種のオトシブミと7種のチョッキリが投稿されています。
詳細は長池公園生き物図鑑を開いて、左中段の図鑑詳細検索を開き、オトシブミ科と入れると出ます。→クリック
まだまだ未発見種がいると思います。
さて最初は、NHKの5分間のオトシブミの動画の紹介です。
ここで疑問が出てきました。
紹介されているヒメコブオトシブミですが、手持ちの文一総合出版のオトシブミハンドブックにはコブオトシブミとして載っている。
ネット上では、本州以西にいるヒメコブオトシブミと北海道にいるやや大きなオオコブオトシブミに分けているのが多いが、大きさ以外には違いがないと書かれているのもある。
ちなみに日本産ゾウムシデータベースでは、ヒメコブオトシブミとオオコブオトシブミに分けてある。
昆虫の種名は結構変わるので難しい。
これは、以前裏高尾で撮影したコブオトシブミ(ヒメコブオトシブミ)です。
![]()
そして、とても興味深かったのは、オトシブミが作る揺籃の多様さの研究です。
日本産のオトシブミは23種(コブオトシブミは2種に分けたある)で、その2/3が一化性で1/3が多化性。
植草も単食性から複数の食草(多いのは21科以上の食草)まで多様で、場所・季節で使い分けている。
また、揺籃の裁断も何種類もある。
これらは、雑誌 生物科学2012年1月号に載っていたもの。
確かに、オトシブミ(ナミオトシブミ)は右巻き左巻き、単裁型両裁型、それも同じ個体がいろいろと行うこともあるというのが、オトシブミハンドブックには出ていた。
もう一つの研究は、揺籃の多様さは寄生者の違いによるという研究があったということ。
幼虫に寄生する寄生蜂の種類が、どのような葉の加工法をとるかに影響しているというもの。
寄生者と植物の相互の進化(共進化)が生物の作り出す構造物の多様さに影響しているとの示唆があった。
あの揺籃の多彩さは、寄生蜂が影響しているとは知らなかった。
詳細は、東北大学大学院生命科学研究科のこちらのサイトをご覧ください。
チョッキリなどはたくさんの葉をまとめて中に産卵するのがいるが、なんであんなに大きなものを作るのだろう?
寄生されにくいからだろうか?
ヤドカリチョッキリというのは、自分で揺籃を作らずハマキチョッキリ類の揺籃に産卵するが、ハマキチョッキリ類は容認しているらしい。
周りに産卵してもらって、寄生蜂による犠牲を軽減しているのだろうか?
昨日は、とても面白い話を聞かせてもらいました。